| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���{���ɂ��� �{�������ɂ́A�O��̐_���̗R���������܂��ł͂���܂����L����Ă��܂��B�ȉ��A������Љ�Ă����܂��B �܂��o�_�i�������j�ɗ��Y���ꂽ�c���V�j���X�T�m�I�m�~�R�g���S����ꊷ���ĎO��̐_�����錏�ł́A���Y�̍ۓ��s�������]���ł��錕���m�Ƃ����҂ɁA��͒j���Ă����炨�݂̂����v�w�Ƌ��͂��ĕA�_�����鎖��\���t�����B��͒j���Ƃ��̍Ȃ́A�_�c�X�̏��_�ɖ�������A���ȂĐg�𐴂ߋF��𑱂���ƁA21���ڂ̖�ɐ_�����������B����ɏ]���A�܂����n�������A��A���S�̎O�i�̍����@��W�߁A�����m���t���Ƃ��A�O�҂��H�v���Â炵�A���S�A�����������đ�ƁA���Ƃ����B ��Ƃ͍��S�A���Ƃ͋��B����ɁA�S�A���ɋ���O�������ĉŏĂ��������A����Ȑ̏�Ŏ�͒j���v�w���A��ɑ�������ƁA���ƂŕS���ł��b���{�������B���l�ɂ��ċ����21���b���A�����H�̋������B�܂����l�ɂ��āA������21���Ԓb���グ���������̋ʂ����B��������Ōq�����ւ̌`��A���̋ʐA�F�̋ʐ����Ōq���H���R�ق��炢��������̕��������ق݂̂��̌`�ɂ������̂���ւ̏�Ɉ��u�����B���ւ͋���Ȃē��l�ɑ���A�����c�X�V�s���_�̌�_��Ə����A��i�̌��Ƌ����A�Ƃ���܂��B ���ɁA���_�V�c�̐��ɎO��̐_��̖͕i������Ă��܂��B ���̌��ł́A�V�ƍc���_�{�̍L�O�ɕS���i���悻�P�W�O���j�l���Ɋ_��������炵�A�l���ɓ�������Ē��A������A�����̉��ɕs��R�i�x�m�R�j�ɓ��Ɍ��̌`���ď���t���A�O�̗��e�ɂ͏��|�~������A�X�ɂ��̑O�ɒI�蕼���ւ����������{���āA���X�̖��̎�X���������̕i�X�������A�J�����̉����������A�O���ɂ͗���݂�A�l���ɒ��A�����߂Ȃ���߂��炵���B�����J���̑O�ɏ\�Ԏl���̍H������A�l���ɗ���݂邵�A���A���A����Ȃ�d����Ƃ����B ���̎d����ɒ������ȂāA�s�V�����T�Βn���߂����A�s������܂��̓�l�̒b��������A�}������v�j�A�F�ڒj���߂��̗��b��������A�o�_��藳�^����イ�܂��A���s�������̗��b��������A�Ó����^�Ô��܂��������A�V�c���߂�݂����͏��݂��Ƃ̂��������A�u�c�c�V�Ƒ���_���A��q����X��ʂ���������肽��O�i�̑���̒ʂ�ɁA���A��A���S���낪����b���č�肠����v�Ɩ������B���l�̒b��t�͕S���̊Ԑ��ɂĐg�𐴂߈ߕ���V���ɂ��A���H�������Đ��߁A�S���̊Ԓb���ɒb���A�����ɉ����ĎO�i�Ɠ��l�̂��̂����グ���]�X�A�Ƃ���܂��B ���m�،Õ��̂��ƂׂĂ�����A��ϋ����[�����̂ɍs�����������̂ł��B �@�@�@�@  ���ꂪ�����ł��i�Ñ㓁�ƓS�̉Ȋw��蕔���]�ځj�B����͂U���I�O���̌Õ��A��ʌ����R�R�Õ�����o�y�������������̕����摜�ł����A���{�����������ꂽ�Ƃ���銙�q�����i�P�R���I�j�̖����Ɣ�ׂĂ����瑻�F�͂���܂���B�S��99.8�����A�n��80.7�����Ɠ��Ƃ��Ă͒���ȕ��ނɓ���܂��B�n�S�������ɂ͋Z�p�I�ɍ���Ƃ���Ă���ۖڔ��������܂��B���͖S�����������t��������h���́A���\�N�Ԑ��q�@�ɖ���Ñ�̓��̌����Ɍg����Ă����܂������A�����̓��̓u�������i�������Ƃ��̊����j�͊��q����̖����Ɖ��瑻�F�͂Ȃ��ƌ��ɂ���Ă��܂��B �摜�̏㕔�����Ƃ��낪�n���ō����Ƃ��낪�n�S�ł��B�ǂ����̎R�̉��i�ʐ^�̂悤�ɂ������܂��B�R�ɂ������Ă���_�͂܂��ɌQ�_�ނ炭���ƂȂ��Ă��āA�O��̐_��̈���ł���u�V�p�_�����܂̂ނ炭���̂邬�v�̖��́A�܂��ɂ��̓��̂悤�Ȑn�̓�������t����ꂽ�ɈႢ�Ȃ��Ǝv����̂ł��B���ݖ��É��̔M�c�_�{�Ɏ�������Ă���Ƃ����V�p�_���ł����A�_�b�ɓo�ꂷ�锪������܂��̂��낿�̔�����o�Ă����Ƃ����A���̓V�p�_���͂��̎���̂��̂��s���Ƃ���Ă��܂��B���ɏ���̓V�c�ł���_���V�c�̍��Ƃ����I���O�V���I�Ƃ���A��ɋ������摜�̑��������ꂽ���ォ��1300�N�O�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �܂�U���I�̎���ɂ͓��̗��j�͂��ł�1300�N�ȏ゠�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����͌��ォ�猩�Ă݂�ƁA1300�N�O�͂V���I�̓ޗǁE��������ƂȂ�܂��B���̌�]�ˎ���̒����ɂ͂���ȑO�̐�����@���S������Ȃ��Ȃ��Ă���Ƃ������Ƃł����A��������ƌ���̓����̓`����300�N�قǂ����Ȃ��Ƃ��]���܂��B�I���O�V���I�����ɋ��������������܂ł�1300�N�Ԃ͂ǂ��������̂ł��傤���E�E�����ւ����N���Ƃ���ł���܂��B �S�����{�Ɏ������܂ꂽ�͓̂ꕶ���������̋�B�k���Ɖ]���Ă��܂����A������������̂͂����炭����A�W�A�A���邢�͌��݂̒����_��Ȃ����肩����{�ɂ���Ă����l�X���낤�Ǝv���܂��B���̈�ɁA�ȑO�ɂ��q�ׂ��悤�������`��������܂��B �퐶����ɓ��{�𐪕������̂́A���N�����Ȃǂ������Ă����S�̕�����������������Ǝv���܂����A���̖����W�c�����{���ړ��������[�g���V�������ړ������Ɠ`�����Ă��郋�[�g�Əd�Ȃ��Ă���̂ł��B�k����B���珙�X�ɐ��Ɉړ����A���ꌧ�A�O�d��������܂Ői�s���Ă��܂��B ���̈ړ��͏��X�ɍs��ꂽ���̂Ǝv���܂����A�����̓A�W�A�S�̂��������헐�̎����������悤�ŁA���ɋI���O�T���I�̒����t�H����̐헐�̍ۂɂ́A���̓��ĊC�ニ�[�g�œ��{�ɂ���Ă������������������悤�ł��B�I���O�P���I���ɂ͒����̍]�삩��k��B���ݒn��ɂ��Ȃ�̈ڏZ�҂��������悤�ł����A������헐��̑O�����̎x�z���瓦��邽�߂̈ڏZ�������悤�ł��B ���݂ɁA���̎����ɑO���͓S������̗A�o���ւ����Ă���Ƃ������Ƃł��B ���̂悤�ɗl�X�Ȗ��������藐���ƁA���R���̖����W�c�̊ԂŔe���������N�����Ă�����s�v�c�͂Ȃ��킯�ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ͂��̌���J��Ԃ��N���������Ƃ͗e�Ղɑz���ł��܂��B����͉���܂����A�������q�`���̌��ɂȂ����̂��A�܂��Î��L�A���{���I��Ҏ[���������A�܂�p�\�̗��ŏ��������ꑰ�i�V���V�c�j�����{�肵���̂����̈�̎����ɂ������A���̌�A���������z�����̂��܂��ʂ̖����W�c���������Ƃ��[���ɂ��蓾��̂ł��B ���Ƃ̒��ׂɂ��ƁA���N�������o�R�����k�A�W�A�l�̓��{�ւ̓n���́A�퐶�����i�I���O�R���I���j����V���I���܂ł̂��悻1000�N�Ԃ�100���`150���l�ɒB�����Ƃ������Ƃł��B����܂Ŕ������ꂽ���W���̌`�Ԃ��琄�肵���ꕶ�l�Ζ퐶�l�̐l����͋ߋE�łP�F�X�A�����n���Q�F�W�ƂȂ�Ƃ������Ƃł��B �Ñ㒩�N�����̉��������ƐV�������E���炬�͑������琼�A�W�A�⒆���A�W�A�̉e�����Ă���Ƃ������Ƃł��B����͂U���I�ɐV���ɕ��������̂ł����A���ɓ��l�̃��[�c���������������悤�ł��B���̉��덑�͐��S�Z�p�ƍ��ےʏ��ӂƂ��Ă��āA�Ñ㓌�A�W�A�̐�i�I�ȍ��������Ƃ������Ƃł��B���덑�����������̂͂P���I���Ƃ���Ă��āA�S�̕���Ƌ���ȋR�n���͂������Ă����Ƃ������Ƃł��B����ȑO�́A���Ƃ��Ɣ_�k�����������悤�ł����A������R�n����������ɂ킽���Đ������A�����������ŁA���̉��덑���k��B��g���i���R���j�ȂǓ��{�ɐB�������Ƃ����Ƃ́A���ł͓����������������̂悤�ł��B�Õ����㏉���i�S���I���j�̌Õ�����n����ʂ̓S�킪�o�y���Ă���̂����Ă��A����͔ے�ł��܂���B �Ñ㕶�����h�����n�����ł͂قƂ�Ǎ����ɂȂ��Ă���̂́A �W�����h�E�_�C�A�����h���q�ׂĂ���悤�ɁA�S���m�ۂ��邽�߂̐X�єj������������܂���B ����̐��S�ł͔R���͂قƂ�ǃR�[�N�X���g���Ă���悤�ł����A�͖̂ؒY���g���Ă��܂����B�S���m�ۂ��邽�߂ɁA�����炭�c��ȗʂ̖؍ނ̂��Ă������̂Ǝv���܂��B�Ñ�̒��N�����ł��A���̂��߂ɎR���ÎR�ɂȂ����Ƃ����L�^���c���Ă���悤�ł��B�ł�������{�ɐV�V�n�����߂��̂́A�S�̔R�����m�ۂ��邽�߂������Ƃ������Ƃ��[�����蓾��b�ł͂Ȃ��ł��傤���B �ɐ��_�{����������O�d���ɐ��n���ɂ́u�h���������݂傤�炢�v�Ƃ����`��������܂��i�Q���j�B�����œo�ꂷ�鋍���V�������Ă�̂��Ƃ����̂͌Î��L�A���{���I�ɓo�ꂷ��f�����X�T�m�I�m�~�R�g�̂��Ƃł��B�f�����Ɖ]���Δ��������}�^�m�I���`�ގ��ŗL���ł����A��ɏq�ׂ��悤�ɁA�ގ�������ւ̔�����S�̌��邬���o���Ƃ���Ă��܂��B���ꂪ�O��̐_��̈�ł���u�V�p�_�����܂̂ނ炭���̂邬�v�ł��B���㌕�����Ȃ��̂邬�Ƃ��]���܂��B ���āA���̈ɐ��n���̓`���Ɠ������̂����㍑�i�L�����j���y�L�т̂��ɂӂǂ��Ɍ�����̂ł��i�Q���j�B����������{�I�ɂ����p����Ă��܂����A����ɓo�ꂷ�镐���_�ނƂ��̂����́A�u�O������n�����������V�_�����A���ɏ��ꂽ�_���Ӗ����閼�ł��邩�͖��m�ł͂Ȃ��v�ƏЉ���T�C�g�ł͉������Ă��܂����A���h�ËL�����̖�E���ߏ����o���Ă��鎭���f�����܂̂ڂ����ɂ��ƁA�h�������`�����x�h�E�B���̐��b�����~���ɂȂ��Ă��āA���[�[�ƃ\�������Ɋւ��郆�_���l�̐��b�Ɠ���A�W�A�̃}���[�����̃��j���܂��̐��b���������ꂽ���̂��Ƃ������Ƃł��B �}���[�����̃��j���܂��̐��b�͌Î��L�_�b�́u�������Ȃ��̔��e�v�̌��ƂȂ��Ă�����̂ł��B���̐_�b�����{���I�ɂ͋L�ڂ���Ă��Ȃ��͈̂���������Ƃ���ł����A�h�������`�����L�ڂ���Ă�����㍑���y�L���c����Ă�����㍑�i�L�����j�ƁA���̓��ׂɈʒu����g�������т̂��Ɂi���R���ƍL�����j�͌×�����S�̎Y�n�ł���A��������卋���̋��_�ƂȂ��Ă����n�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B��B�k�����̉F�����i�啪���j�͓ꕶ�������ɓS�������Ă��Ă���A�S�̎�v�ȋ����n�ł����B���̌�A�o�_�i�������j�Ƌg���i���R���j�������킯�ł����A���ꂼ�������������������Ă����悤�ł��B �Q�O�O�R�N�ɁA�퐶����̎n�܂�͏]���̐������T�O�O�N�قǑk���āA�I���O�P�O�O�O�N���ɂȂ�Ƃ����w�������\����܂������A���̋c�_�͂P�X�V�V�N������s���Ă����悤�ł��B�Ƃ��낪��ɏЉ�������f���͂�������Q�O�N���O�̂P�X�T�V�N�ɁA�啪���̍��������i�F���j�ɐ��S��n��݂����̂́A�g�C����n�Ƃ���^���V���D�̈ږ����Ƃ������\���Ă����̂ł��B�������ɂ��ƁA�\����������������^���V���D�ł���Ă��������W�c�i�G�u�X�l��t�F�j�L�A�l�j�͓����A�^�C�̃o���`�F���ɐ��S��n���\���Ă������A���̒n�̖؍ނ��̂�s�������̂ŁA�I���O�P�O���I����B�̉F���ɓn���Ă����Ǝw�E���Ă���̂ł��B ��������ɕҎ[���ꂽ���쎮�̊��l�\��@���ɗ��̂Ȃ����瓁���ɂ��Ă̋L�q�����グ�Ă����܂��B �G�������������������� ������\����A ������\�ܓ��A�Z����\�����i���̋L�q�͍�҂̘r�O�̈Ⴂ�ɂ�邩���� �������� �v���܂��j�B�n�J�l�i�|�j��j�� �n�J�l�����킹�A���Ȃ���ɐn��ł��Ɠ�� �B���i���j��ɍ��i�������Ɓj�l���B�e�u�i�r�u�j��������A���i�Ă�����j��ɒ���������A�����܂Ƃ�����A���i�d�グ�����E���o���j ����B����b�i������j�A�v���c�c����ƈ���B�����O���i���̉��h��O��j�A���̂Ƃ��h�閈�Ɉ�����������ƁB�����i���̒��h��j��ՁA�h�閈�Ɉ���������B�̋��i����j����邱�Ɠ���B�e�����炷�� �A�����i�܂���j��ɏēh�莽�̍�Ɠ���B���r�i�����j��ɕ��Z���܂������A���E��ɒ����i���̒��h��j�������ƈ���B�Ԏ��i�d�グ�h��j �����ՁB��y�ѕ�����Ɉ���B �����͊����ŁA���r�A���艼�����t�����Ă���Ƃ���͂���ɏ����܂����B�p�\�R���ŕ\���ł��Ȃ������̓J�^�J�i�ɂ��Ă����܂����B���߂͎��̉��߂ł��̂ŊԈ���Ă��邩������܂���B�ԈႢ������܂����炲�w�E�����Ə�����܂��B �n���b��̖��H�u���ߐ��G�����@����Ђ��v�͖������N�A�����̖��品�H�ꑰ�̉Ƃɐ��܂�Ă��܂��B���͓��H�E�^�����r�A�c���͕đ�˂̌�p�b��ł���A�܂��㐙�Ƃ̂������b��ł����������^�֍j�r�A���̎o�̎q�͍]�˂̓��H�E�Γ��Ƃ̗{�q�ƂȂ�A��ɓ���Ƃ̂������b��ƂȂ�������ځE�Γ��^���������ꂩ���ƂȂ��Ă��܂��B�c���̌Z�����H�Œ��^�֍j�p�A���̎k�q�i���ƂƂ�j���V�X�����i�]�ˎ��������疾������j�̑�\�I���H�ŎR�@���ł��B ���ߐ��G�����܂�ĂQ�N��̖����X�N�A�p���߂��o����܂��B��������ɓ����W�̎d�������Ă����E�l�͐E���������ƂɂȂ�܂��B����͓��b����͂��߁A������𐧍삵�Ă��������t�A���G�t�ȂǑ����̕���ɋy�сA�Ȃ��ɂ͎��n����������҂������Ƃ������Ƃł��B ���ߐ��G�̕��e�A���ڍj�r�i�^�����r�j�͎m���ł������Ƃ����������炩�A�p���ߌ�͉B�������A���̒�͎���ځE�Γ��^������̗{�q�ƂȂ�A����ځE�Γ����i�Ƃ��Ȃ��Ƃ��ē����b�肩��n���b��ւƓ]�g���܂����B����ł��A��ɐ��q�@�̓����ʂ��𖽂���ꂽ��A�����Z�N�ɊJ�Â��ꂽ�E�B�[�������ɓ������o�i�����肵�Ă��܂��B ����17�N�A10�̐��ߐ��G�i�{���F�����A�j�́A�f���ɂ����锪��ځE�Γ����i�ɓ��債�܂��B�Γ����i�̑��q��������ŁA���ɏC�Ƃ������Ƃ������Ƃł��B ����G�Y���u���ߐ��G�v�ɂ��ƁA����33�N�A���ߐ��G�Q�V�̎��ɓ�����Ɏ���̓����o�i�������Ƃ����邻���ŁA�����A�Ӓ�����������̓������Ď��̂悤�ɂ��������Ă����Ƃ������Ƃł��B�����l�H���u�����āA���̓��͒��^���ߐ��G�Ɩ������Ă���܂����E�E�v�A���̐l���H���u���O�`�̍앗�����A�V�쓁�̂悤����Ȃ��Ƃ��낪����܂��v�A�܂����̊Ӓ���H���u���̍l���ł́A����͖����̌Ó��ɍ��̐l������������̂ŁA�o�i�҂���X�̊Ӓ�͂������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���v�E�E�Ƃ������ƂŁA���Ǐo�i��Ƃ��Ďt���Ă��炦�Ȃ������Ƃ������Ƃł��B��N�A�Ȃ����H�̉Ƃɐ��܂�Ȃ��瓁��ł��Ȃ��̂��Ɛu�˂�ꂽ���G�́A��̈펖���q�ׁA�u���̎��ȗ��A���͓���ł��Ă���܂���v�Ɠ������Ƃ������Ƃł��B ���̂��Ƃ���A�n���b��֓]�E���Ă����Γ����i�̍H�[�ł́A �����b��̋Z�p�����ߐ��G�ɓ`�����Ă������Ƃ��f���܂��B�����A�Γ����i�̎t�A�Γ��^����������݂ŁA���l�����قǂ������悤�ł��B�^������Ƃ����A���O�`�̍쓁�ӂƂ��Ă��āA�{�̂ɂ͂Ȃ����ɂ��{�ʂ̒��q�n�����傤���@�͂�����j�]�Ȃ��Ă��グ�邱�Ƃ��ł���̂́A�V�X�����̓��H�̒��ł͂��̐l�����������Ƃ������Ƃł��B���q�n�����Ă��ɂ͍|�̏���������Ƃ������ƂŁA����ɉ����A�n���ɁA���̌������܂Ŕj�]�Ȃ����i��r�I�傫�߂̗�������g�D�œ���Ō��邱�Ƃ��ł���j��t���邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂��A�Z�p�̍�������Ă��܂��B ���ꂩ��A��ɋL�q�������ƂŁA���ߐ��G��̓������ĊӒ�����Ó��ƌ��ԈႦ���Ƃ����Ƃ���������[���̂ł��B�Ó��Ƃ͍]�ˎ���ȑO�i�c���ȑO�j�̓��̂��Ƃ������܂����A�������㓖���̐V�X�����̓��Ɣ�ׂ�ƒn�S�������̗l�q�ł��̈Ⴂ���������邱�Ƃ��ł��܂��B�Ó����̎��̎���敪�́A�]�ˎ��㏉�߂������܂ł�V�����A�����č]�ˌ�����疾������܂ł�V�X�����Ƃ��Ă��܂��B���̋敪�͒n�S�̈Ⴂ�ŕ����Ă��錾�������Ă��������炢�ł��B����قLjႢ�܂��B�ł�����A���̊Ӓ�������Ă���قǂ̐l������������ԈႦ��قǂł�����A���G����������͂�قLj���Ă����̂ł��傤�B���Ќ��Ă݂������̂ł��B ����m�g�j�e���r�ŁA�_�ː��|�̗n�z�F�̉��z�̂��Ƃ��ԑg�Ƃ��ĕ��f����Ă��܂����B�ԑg�̂Ȃ��ŁA�_�ː��|�Ƃ�����Ђɂ͐��L���Ƃ�������������Ƃ������Ƃ��Љ��Ă��܂������A�L���L�S����Ă��̂��ƂőL�����Ƃ��Ă�Ă��܂��B��ʓI�Ɂu�S�v�Ɖ]���Ă�����̂̂Ȃ��ŁA�Y�f�̊ܗL�ʂ�1.7���ȏ�̂��̂�L�Ə̂���̂������ł��B�Y�f�̊ܗL�ʂ�1.7���`0.03���̂����|�͂����A0.03���ȉ��̂��̂�S�Ə̂��܂��B�܂�A�Y�f���������قǏ퉷�ōd���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�ł�������I�ɂ́A�n���K�l�̂悤�ɏ퉷�œ�炩�����̂�S�Ə̂��A�n���Ɏg���悤�ȍd���̂��͍̂|�A�S�r�Ȃǒ����Ɏg�����̂�L�Ə̂��Ă��܂��B �ԑg�ŁA�n�z�F�ł�1500�x�ō|������Ɛ�������Ă��܂������A�����ō��ꂽ�|�����Ɏg����̂��͂͂����蔻��܂���ł����B�������č��ꂽ�|�͎g�p�ړI�ɂ��A���z�p�S���⎩���ԗp�Ԏ��A���ꂩ��n���p�Ȃǂɓ��H�����̂��Ǝv���܂����A���{���ɂ͎g�p����܂���B���{���̏d�v�ȗv�f�ł���n�S�i�����ˁj�̍Ⴆ��������́A�n�z�F�ō��ꂽ�|�ł͏o�Ȃ��̂������ł��B���{���Ɏg����|�͓��{�×�����́u������v�Ƃ����F�ō��ꂽ���̂��g�p���܂��B���̘F�ł͊Ҍ�����Ƃ��̉��x��1200�x�`1300�x�ƁA���Ⴂ���ōs����Ƃ������Ƃł��B1500�x�ȏ�̍������ƕs�������������Ă��܂��̂������ł��B �n���Ƃ��Ă̐��\�����Ȃ�A���ݍ���č����|�̕����͂邩�ɗD��Ă��܂��B���Ƃ��A���͍��h�ȂǍd���؍ނ����n���̓n�C�X�|�̂��̂��g���Ă��܂����A�n�C�X�|�͍|�ɃN�����ƃ����u�f����^���O�X�e���Ȃǂ����������̂ł��B���̃n�C�X�|�̐n���͋��x�ŁA�n���ڂꂷ�邱�Ƃ��Ȃ��A�Y�f�������̍|�̂��̂�萔�{�i�ꂵ�܂��B�ł����A�ǂ̂悤�ȗD�ꂽ�u�Ō����グ�Ă��Y�f�|�̂悤�ȍႦ��P���͏o�܂���B ��ɏЉ���n���b��̖��H�E���ߐ��G�́A�t��������{�×��̋ʍ|�����m�|�i�A���|�j�̕����n���Ƃ��ėD��Ă���̂ŁA������g���悤�ɓ`�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B ���{���͊��q����(�P�R���I�j�Ɋ������ꂽ�Ƃ���Ă��܂����A����͎��p��̊����x�Ƃ��������A�ӏ�̊����x�������Ă���Ǝv���܂��B�L�^�ɂ��ƁA���Ƃ������͕̂�������̍�����ӏ܂̑ΏۂƂ�����A����Ɠ����悤�ɁA���g�̒n�S��������n���͂����̔������Ȃǂ��ӏ܂��Ă����悤�ł��B ��ɏq�ׂ��悤�ɁA�S�Ƃ������̂��퐶����ɓ��{�ɂ����炳�ꂽ�Ƃ���A���q����ɓ������������܂�1800�N�قǂ������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B���q����̓��̐���Z�p�i���ɓS�̐��B�Z�p�j�͍]�ˎ���̒����ɂ͓r��Ă��܂����Ƃ������ƂŁA�Ȍ�̍�҂͊��q����̖����ɔ��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă���Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��悤�ł��B����͌��݂ł������ŁA��������ƍ]�ˎ��ォ�琔���Ă��悻300�N�Ԃ���͑������Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�Ƃ������Ƃ́A���q����ɔ��邱�Ƃ��ł���ɂ́A����1300�N������Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���E�E ��ɁA���{���͓��{�×��́u�������v�F�Ő��|���ꂽ�|���g���Ƃ������Ƃ��q�ׂ܂������A����͍��S�������Ƃ��A�Y�ʼn��x�������Ҍ��A���o���ꂽ�|�ŁA�������ē���ꂽ�|�̂����ł��D��Ă�����̂��ʍ|�Ə̂��܂��B���{�������ꍇ������O���Ɏg���A�����͒Y�f�ʂ̏��Ȃ��_�炩�߂̓S���g���Đc�ɂ���Ƃ��������Ƃł��B�������Đ܂ꂸ�Ȃ��炸�A�Ƃ������{���̓��������o����܂��B �Ƃ��낪�ߔN�A�Ó����i�������ォ����y���R����j�̓��́A�O���̍|�Ɏg���Ă���̂͋ʍ|�����ł͂Ȃ��Ƃ����������H���g������������A���{���������̊��q����𗽂��ɂ́A�܂����̂��Ƃ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ��������o����Ă��܂��B�S�̌����҂̂Ȃ��ɂ́A�Ó��̍|�͑L�S�������Ă���̂ł͂Ȃ����Ə�����l�����������ł��B���ɓ��H�̂Ȃ��ɂ͑L�S���g���Ă���l������悤�ŁA������s���Ă���l�����́A���g�������鎎�s������o�A���\�N�������ĒH�蒅�������_�̂悤�ł��B �Ó����̓��ƐV�����i�]�ˎ���j�̂�����r����ƁA�n�S�������̈Ⴂ�͈�ڗđR�ł��B����I�ɈႢ�܂��B�Ƃ������Ƃ́A����́A��͂�g���Ă���f�ނ̈Ⴂ�A���邢�͏����̎d���̈Ⴂ�Ƃ����l�����Ȃ��̂ł��B���ꂩ��A���ݓ`����Ă���쓁�Z�p���]�ˎ��㒆���ȍ~�̂��̂ŁA����ȑO�̂����͑S�������Ă��Ȃ��̂������ł��B�������Ă݂�ƁA�S���Èł�i��ł����悤�Ȃ��̂ł��B����ł��A���̂��ƂɑS�Ă������Ď��g��ł���l����������Ƃ������ƂɁA�����ƂƂ��ɁA�[�����������Ă��܂��̂ł��B ����͊y����ɂ��]���邱�ƂŁA�y������A�������Ƃ������Ƃ͐悪�S�������Ȃ��Èł�i�ނ悤�Ȃ��̂ŁA��T��̊������������̂͂Ȃ��̂ł��B���̊����ɂ́A�Ɛ[���t�����������Ȃ��A�Ƃ����M�O�̂��ƂɎ������X�T���𑱂��Ă��܂����A���̐M�O�͎��ɂ͗h�炬�����ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B���̎��ɁA���{���Ɏ��g��ł�����X�̋��x�ȒT���S�ɂ���܂ŗE�C�t�����Ă����̂ł��B ���́u�n�������炦�v�Ɏg���u�����v�̍�҂́A���H���b�����|���g���̂���ʓI���Ƃ������Ƃł����A���؈ꐬ���́A�f�ނ̍|�������ō��̂������ł��B���؎��̗͐̂L���ȒՂ��ʂ��i�͎ʁj���Ƃ��Ȃ����Ă��܂����A���������ʂ��Ƃ��ɂ͓��ɋ�J�����Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ��A�����ō��S����|�����o���u���Ɛ��|�v�����邱�ƂɂȂ������������������Ƃ������ƂŁA���s����̖��悤�₭���������Ƃ́A�����Ղ̎����A���͋C���o�����߂ɂ͐���ނ̎Y�n�̍��S��g�ݍ��킹��K�v������Ƃ������Ƃł����B���͂�������p����A����܂łɂȂ��S�����o�����Ƃ��ł��邩������Ȃ��Ɗm�M���A�S���̍��S������̏W���������ł��B �k�͖k�C���̒�����������܂�������͎�q���܂�50�������̍��S��S�z���̏W���A����炩����o�����|���g���Ղ����삳�ꂽ�B�����̍�i�͏��a�T�W�N�ɍs��ꂽ�W�ɏo�i���ꂽ�����ł����A�����̈Ⴂ�ɂ��S���̈Ⴂ�͏��߂ĒՂ�����l�ɂ���ڗđR�������Ƃ������Ƃł��B�Ղ͓��ƈႢ�A�\�ʂɎK�т�t�������d�グ�܂����A���̎��̎K�ѕt���̖�i�ɂ���Ă�����������Ă��܂��̂ŁA�S�̎Y�n�ʂ̎���i�ɂ͓������@�ŎK�ѕt�����Ȃ��ꂽ�̂��Ǝv���܂��B �܂����́A�l�X�ȎY�n�̍��S������o�����|���g�����n�����{�����ꂽ���Ƃ�����Ƃ������Ƃł��B���̒��ɂ͏o���̂悢���̒n�S�i�����ˁj�̂悤�����ɂ�����ɂ������L�x�ɕt���A�n���̓������ǂ����̂������������ł��B�Ƃ������Ƃ́A���R�̂��Ƃł����A���̏o���ɂ��Ă��|�̌����̉e�����傫���Ɖ]���܂��B �����ł����A�y��Ƃ̋��ʓ_�������яオ���Ă��܂��B���鉹����邽�߂̑f���i�j�A������܂Ƃߏグ���҂̋Z�ʁA���f�́A���A�Z���X�ȂǂȂǁE�E�B����ɂ���Ċy��̃��x���͎����ƌ��܂��Ă��܂��܂��B�܂��������{���̐��E�Ɠ����ł͂Ȃ��ł��傤���B �������낢���̂ł��B �]�ˎ���̋��H�t�⍪�t�E���Ďt�̋Z�p�̍����ɂ͑S�������Ă��܂��̂ł����A����𗽂����̂���̎���ɍ��ꂽ�Ƃ��������ɂ܂��܂������Ă��܂��̂ł��B����͑��ɂ����݂��A���̈�ɓ��̒Ղ�����܂��B 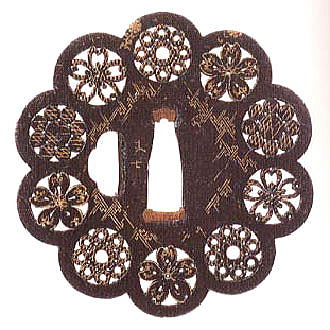 ����͍]�ˎ��㏉���̖��H�u�����v�ɂ��u����j�䓧�ۛƒՁv �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���c�@�l�i���ɏ����j  �����Ă���͌���̒Ս�Ƃł���ʉ��r�s���ɂ���i�u���ӓ��ۛƒՁv�i�S���{������s-�}�^���{���̐S�ƋZ-����]�ځj�ł��B����ɂ͌����ȁu���������v���{����Ă��܂����A�Ղɂ����܂Ő��k�Ȏ�����������萋�����̂͗��j�㏉�߂Ăł͂Ȃ����Ɖ]���Ă���قǂł��B���ۛƂ̋Z�p�����炵�����̂ł��B����͂�����[�U�[���H�ȂǁA����̉��H�Z�p�ōs�����̂ł͂Ȃ��A�̂Ȃ���̎��Ƃō��ꂽ���̂ł��B �Ñ�̐��S �g������ |